 セシル
セシルこんにちは,心理ブロガーのセシルです🍀
今回は,「いじめの問題と解決策」について,私なりの考えをお話しさせていただきます。
私は,『いじめ問題』は人間社会における終生の課題であると考えております。
『いじめ』について
『いじめ』とは??

『いじめ』とは,「当該児童生徒が,一定の人間関係のある者から,心理的,物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの」とされています(文部科学省, 2019)。
ただし,いじめは学校だけではなく,どこの社会でも起こりうる問題です。
たとえば,職場でのいじめや嫌がらせ,近所や地域社会における仲間外れのようないじめ,家族や兄弟・姉妹からのいじめなどがあります。
最近では,インターネットやSNSにおけるいじめもあり,特定のグループで仲間外れにされたり,無視されたりすることもあります。
インターネット上では,一定の人間関係のない不特定多数の人から誹謗中傷されるということもありますね。
いじめは,人が物心ついた頃から高齢者になって余生を過ごすまでずっと起こりうる問題といえるでしょう。
相手をからかうような些細ないじめから,ニュースで報道されるような “重大ないじめ” まであり,
たった1回のいじめから長期間に及ぶいじめまであります。
いじめの原理

世の中のいじめは,すべて『弱い者いじめ』です。
いじめとは,基本的に力や立場の強い側が弱い側を攻撃することをいいます。
時々,組織のトップ等が大勢の人からバッシングされることがありますが,
それは個人が集団化することによって,トップより力をもつからであり,力の原理は同じです。
(※もちろん,不正等が非難されるのは当然のことであり,必ずしもいじめであるとは限りません)
つまり,いじめとは,強い側が弱い側をいじめるという構図しか成り立たないため,世の中には弱い者いじめしか存在しないと考えられます。
逆に,弱い者1人で強い者をいじめることはできませんよね。
有名ないじめ事件

いじめ事件のなかでも『旭川女子中学生いじめ凍死事件』や『大津中2いじめ自殺事件』は,全国的に有名ないじめ事件です。
どちらにおいても,いじめ被害を受け続けていた生徒が亡くなられていますから,忘れることができません。
とくに,『旭川女子中学生いじめ凍死事件』のように,性的な画像を周囲に拡散する行為は,命に直結する重大な問題です。
短絡的に感情論に走ってはいけませんが,強い憤りを覚える方がたくさんいらっしゃるのも理解できますし,私も同じ気持ちです。
いじめの問題と解決策を考える
「いじめの問題と解決策」について,私なりの見解をお話しさせていただきます。
『いじめ』の問題

いじめは,いじめられた被害者の心に大きな傷を残します。
あるいは,加害者にとっても心の傷になることがあります。
いじめられた経験や心の傷が原因で,精神疾患(e.g., PTSD, 社会不安障害)になることも少なくありません。
いじめによって,傷つけられた心が被害者の人格形成にまで影響を及ぼし,その後の人生に重大な影響を与えることもあります。
また,被害者の心にはいつまでも傷が深く残り続けるのにも関わらず,加害者はいじめたことすら覚えていないということはよくあります。
あるいは,加害者によっては,大人になってから「酷い事をしてしまった」と自責の念にとらわれ,自己肯定感をもてなくなることもあるかもしれません。
『いじめ』の解決策
いじめの解決策として,『いじめ問題の教育』と『社会システムの改革』が考えられます。
いじめ問題の教育

前述のように,いじめはどこの社会でもあります。
決して正当化できる行為ではありませんが,それが人間あるいは人間社会というものかもしれません。
いじめの問題を解決するためには,
人間という存在を客観的に見つめて,人間の負の側面から目を背けずに学ぶ必要があると思います。
単純に「いじめをする人間が異常者だから」ではなく,
いじめは誰でも加害者になりうるものとして認識して,自分自身を啓発していくことが大切です。
(※もちろん,明らかに加害者の人間性に問題がある凄惨ないじめ事件もあります)。
また,いじめの問題においては「いじめられる側にも原因がある」ということが指摘されることがあります。
たしかに複雑な人間関係の問題において,10対0のケースは稀かもしれません。
しかし,どちらに原因があるのかという議論は非常にナンセンスです。
大事なことは,被害者にも原因があろうがなかろうが,人を絶対にいじめてはいけないということを教育することです。
そして,もしも「いじめ加害者」になってしまった時には,どのように対応すればよいかも教育する必要があります。
『いじめ加害者=異常者・犯罪者』のようなレッテルでは,加害者も意地になって認めることができないかもしれません。
誰でも人をからかってしまったり,失敗することはありますし,その時にどう対応するかが大切です。
多くの場合,加害者が心から反省をして,被害者にそれが伝われば赦されるのではないかと思います(ただし,被害が重大なケースを除きます)。
社会システムの改革

いじめの問題を解決するためには,『いじめ問題の教育』だけでなく,『社会システムの改革』も必要です。
学校でのいじめ

いじめ問題において,最も人々の関心が高いのは,“学校でのいじめ” です。
学校にもよるかもしれませんが,学校側がいじめを否定・隠蔽することはよくありますね。
加害者が保身のために嘘をつくのは心理的にありうることですが,
教育機関である学校がなぜいじめを隠蔽するのかということが,いま1つの社会問題になっていると思います。
学校固有の問題だけではなく,いじめ(学校にとって不都合なこと)の隠蔽を促進するようなシステムにも問題があるのではないでしょうか。
もちろん,いじめを隠蔽する学校を看過することはできません。
しかし,あちこちで隠蔽が横行するのには,社会のシステムそのものにも問題があるように感じます。
つまり,システムそのものを変えれば,いじめの隠蔽問題を減少させることができるかもしれません。
具体的には,学校側(あるいは校長先生)がいじめを認めることで損をするようなシステムではなく,
いじめを発見して,積極的に解決することにメリットがあるシステムに変える必要があると考えられます。
いじめを発見して積極的に解決に取り組むことが評価されるシステムであれば,いじめの早期発見にも繋がります。
また,いじめの発見やいじめのアンケートにおいても,
第三者機関が担当したり,アンケートもインターネットなどで自宅で実施できるものがよいと思います。
他の生徒がいる教室でアンケートに回答させたり,先生あるいは後ろの席から回収したりするのは,方法論として論外ですよね。
そして,学校外や休日に起きたいじめであっても,生徒が関わるいじめであれば,保護者はもちろん学校側が介入するべきです。
他校の生徒が混ざっているケースもあるので,やはり第三者機関の介入は必須であると考えます。
職場でのいじめ

学校だけでなく,社会人になってからも職場でのいじめがあります。
悪口を言われたり,嫌がらせ,ハラスメント,仲間外れのようなことが起きています。
いじめやパワーハラスメントが社会の厳しさであるかのように,すり替えられて正当化されることもあります。
そして,いつも被害者がいじめを訴えることで問題が発覚しますが,
被害者が訴えるまでには心理的・物理的ハードルが高く,ほとんどが泣き寝入りしている現状があると思います。
職場でのいじめにおいても,やはり第三者機関の介入が必要です。
たとえいじめがなくても,第三者機関によって定期的に調査が行われる必要があります。
ただ,古い体質の会社やブラック企業の場合,いじめやハラスメントの問題が軽視されていて,個人の力ではどうすることもできないかもしれません。
現状では,労働基準監督署や弁護士などに相談したうえで,できるだけ早い段階で転職するのが良いかもしれませね。
定年まで同じ職場でやっていく方針であっても,急に辞めることもあるかもしれませんから,
加害者との会話をICレコーダーに録音したり,被害をノートに記録しておくことをお勧めいたします。
たとえ我慢して仕事を続けたり,問題が自然と解決したとしても,
これらのことが無駄になることはありませんし,
ノートに書くことは自分の心を整理したり,ストレスを解消する方法としても有効です。

地域社会でのいじめ

学校や職場に限らず,地域でもいじめはあります。
それは近所づきあいや町内会,地域のサークルなどで起こります。
1人だけ挨拶をされなくなったり,仲間外れにされたり,村八分のようなこともあります。
地域の問題に,第三者機関が介入するというのはあまりないでしょうから,社会のシステムを変えるのは難しいと思います。
引越ししてしまうのが最も早い解決方法ですが,経済的な事情や色々な事情で簡単に引越しできないことが多いと思います。
一定の人間関係で問題が起きていて,度が過ぎる場合は,弁護士に相談されるのが良いと思います。
また,できる限り波風を立てずにやり過ごすという方法でも,少しずつ問題が薄れていくということもあります。
悔しいかもしれませんが,あえて笑顔を振りまいて,周囲を懐柔するというのも手ですし,
インターネットやSNSを通して,日本全国や世界中の人と関わることで,別の方へ気を向けて心理的負担を減らすのも有効です。
家庭内でのいじめ

いじめは家族間や家庭内でも頻繁に起きています。
親からの虐待,兄や姉からのいじめなど,実際は家庭内でのいじめが最も多いのではないでしょうか。
同じ家に住みながら,家族と距離を置くというのは非常に難しいですよね。
私も兄からの暴力と暴言に長年苦しんでいました。
家庭内でのいじめも社会のシステムで対応するのが難しい問題です。
警察は民事不介入ですし,世間体もあり,簡単に警察を呼べないという事情もあると思います。
児童相談所の方もご苦労されていると思いますし,家庭内でのいじめや虐待は介入が難しい問題だと思います。
ただし,家族といえども,暴力は犯罪ですから法的措置を取ることはできます。
暴力を伴ういじめを受けている場合は,それが親や兄弟・姉妹であっても,すぐに警察を呼ぶべきです。
警察を呼ばれるということを加害者に一度学習させれば,それが抑止力になります。
私の場合,母と兄と私の3人暮らしでしたが,母は全く助けてくれることはなく,世間体を気にして,警察を呼ぶことには猛反対でした。
家族で一番年下であった私は,警察を呼ぶという発送がありませんでした。
後から考えれば,当時,警察を呼べばよかったと少し後悔しております。
また,学生の方であれば,学内の相談機関に相談して,適切な第三者機関に繋いでもらえるかもしれません。
友人,親戚,近所の知り合いの家などに逃げられる場合は助けを求めてください。
目上の家族に対して,心理的な抵抗があるかもしれませんが,
暴力や暴言を伴ういじめをする家族に遠慮をする必要はありません。
家庭内でいじめが起きている場合は,誰が加害者であるにせよ,
親がまったく機能していない場合がほとんどであり,完全に親の責任であると思います。
そして,いじめが起きている以上,親が責任を自覚しているケースは稀です。
私は,兄より強くなるまで耐え続けましたが,世間体を捨てる覚悟で警察を呼ぶべきだったと思っています。
インターネットやSNSでのいじめ

現代では,インターネットやSNS上で,いじめのターゲットにされるというケースも増えています。
一定の人間関係のあるなかで,1人だけブロックされたり,仲間外れにされたりすることもあります。
また,人間関係のない見知らぬ人から誹謗中傷の被害に遭うこともあります。
インターネットやSNSでのいじめについては,
インターネット上の「モラルの向上」や「加害行為に対する厳罰化」が有効であると考えられます。
こちらについては,下記の記事で詳細に説明しておりますので,ご参考にしていただけましたら幸いです。
いじめの問題と解決策を考える:まとめ
・いじめは,いつの時代もどこにでも存在する
・人間の負の側面から目を背けずに,いじめ問題を教育することが大切
・いじめが発生しないように,また発生した場合に適切に対応できるシステムを構築する
・第三者機関の積極的な介入が必要
いかがでしたでしょうか。
今回は,あくまで私なりの考えをご紹介させていただきましたが,
学校や教育関係者の方々のほうがたくさんの考えをもってらっしゃると思います。
もし,ご意見等がございましたら,お問い合わせやTwitterのDMなどで教えてくださいましたら幸いです。
勉強させていただいたうえで,記事に反映させていただくこともございます。
そして,いじめの問題と解決策において,とくに第三者機関の介入が重要である旨を説明いたしましたが,時間や予算の都合上,容易ではない事情もあると思います。
先生の前で堂々と行われるいじめは少ないでしょうし,被害者にもいじめられていると認めたくないプライドもあるでしょうから,
教員の先生方が気づきにくいという事情もあると思います。
とくに,家族や兄弟からのいじめは第三者の介入が非常に難しい問題です。
さらに,『いじめ問題の教育』および『社会システムの改革』によって,いじめを減少させる(または早期に解決する)ことを実現できたとしても,
世の中から「いじめ」が完全になくなるわけではありません。
どんな犯罪もなくならないように,必ず悪い人間は一定数います。
悪いことがカッコいいとさえ思っている人もいます。
このような方々に対しては,厳罰化で対応するべきです。
いじめは人生に重大な影響を及ぼす問題ですから,心から無くなってほしいと切に願っております。
最後まで読んでくださった方,ありがとうございました🍀
 セシル
セシルこの記事が気に入ったらぜひシェアしてくださいね🍀

\ 不登校のお子さんを支援するサービスはこちら!/



\ 今すぐ仕事を辞めたいあなたの味方です!/


\ おすすめの『カウンセリング』はこちら /

\ おすすめの本・電子書籍はこちら!/
【引用文献】
文部科学省 (2019). いじめの問題に対する施策
いじめの定義 文部科学省ウェブサイト
Retrieved from https://www.mext.go.jp/a_
menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm
(2022年4月5日)





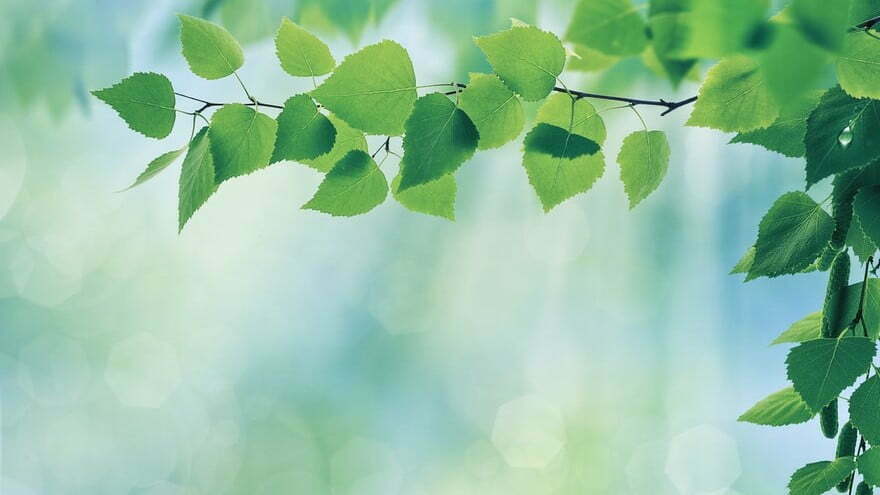















コメントを書いてみよう (^○^)