 セシル
セシルこんにちは,心理ブロガーのセシルです🍀
今回は,「マスコミとインターネット・SNSにおける誹謗中傷の問題と解決策!!」について,私なりの見解をお話しさせていただきます。
誹謗中傷とは??

『誹謗中傷』とは,他人の悪口を言ったり,名誉を傷つけることです。
誹謗が「他人の悪口を言うこと」であり,中傷とは「根拠のない悪口を言い,他人の名誉を傷つけること」を意味します(スーパー大辞林)。
『批判』とは「物事の可否に検討を加え,評価・判定すること」,「誤っている点やよくない点を指摘し,あげつらうこと」です(スーパー大辞林)。
したがって,誹謗中傷が他人を傷つける悪口であるのに対して,批判は物事に対する評価や指摘であるため,両者の違いは悪口を含むかどうかの違いということになります。
批判は,自由な意思表示でもあり,憲法第21条で保障されている「表現の自由」からも正当な権利であることが分かります。
対して,誹謗(悪口)は,事実の有無に関わらず成立するものであり(たとえば,髪の薄い人に対して「ハゲ」などと言う),誹謗中傷,暴言や脅迫は犯罪に該当する場合があります。
ただ,誹謗中傷と批判の線引きが難しい場面は多々あると考えられます。
また,誹謗中傷と批判が混ざっているケースもよくあります。
たとえば,「信号無視をしてはいけない! ルール違反をする人は頭がおかしい」などの場合,赤字の部分が誹謗に該当します。
マスコミにおける誹謗中傷

マスコミとは,マスコミュニケーションの略語であり,テレビ,新聞,週刊誌,インターネットなどを通して情報を伝達することです。
マスメディアは,テレビ,新聞などの媒体そのものを指します。
マスコミにおける誹謗中傷の特徴
マスコミの社会への影響力の強さは,インターネットの個人ユーザーの比ではありません。
マスコミが世論を誘導して,誹謗中傷を扇動することさえありえます(そもそもニュースや情報がなければ,インターネットユーザーは誹謗中傷のしようがありません)。
とくに週刊誌における有名人等に対する誹謗中傷はテレビ報道よりも厳しいです。
マスコミとインターネットユーザーの違いは,マスコミの影響力の強さに加えて,マスコミが報道によって利益を得ているという点です。
(※一部,誹謗中傷に該当する記事などを執筆して,利益を得ているインターネットユーザーはいます)
以上のことから,マスコミの責任は重大であるといえます。
マスコミにおける誹謗中傷の解決策
昨今では,インターネットやSNS上での誹謗中傷が問題視されていますが,
マスコミがまず社会のお手本となって,誹謗中傷を根絶する必要があると思います。
マスコミのことを棚に上げて,インターネットユーザー(いわゆるネット民)を非難しても,
マスコミがこれまでに行ってきた誹謗中傷に該当する報道などを指摘されるのが目に見えています。
マスコミによる誹謗中傷を防ぐためには,マスコミの報道に関するルールを詳細かつ徹底的に定める必要があると思います。
ルール違反に対する罰則も絶対に必要です。
マスコミが社会のお手本となったうえで,世論に向けて,誹謗中傷に警鐘をならし続けることのほうが効果的であると考えられます。
インターネット・SNSにおける誹謗中傷

インターネット・SNSにおける誹謗中傷の特徴
近年,インターネットでは,特定の人物に対して,批判的なコメントが殺到する炎上という現象が問題視されています(山口, 2015)。
炎上の中には誹謗中傷に該当するコメントも多く見られ,
インターネットやSNSにおける誹謗中傷には,マスコミの表現を遥かに超えた暴力的かつ差別的な表現が含まれることも少なくありません。
そして,匿名による書き込みがほとんどです。
中傷された有名人・芸能人に対して「見なければいい」とアドバイスされる方もおられますが,
インターネット上における誹謗中傷は,被害者以外の多くの方が目にするものであり,「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などに該当する場合があります。
たとえば,「バカ」などと書きこまれて,本人が気にしないようにしたとしても,
インターネット上で不特定多数の人が目にすることによって,中傷された方の名誉が棄損されてしまうのです。
虚偽の噂を流されれば,企業や有名人などは仕事に大きな支障や損害をきたすこともあります。
被害者が,加害者に損害賠償を請求する訴訟も増えてきており,
過度な誹謗中傷によって,追い詰められ続けた有名人が自死を選択するという悲しい出来事も増えていますね。
また,インターネットやSNSにおける誹謗中傷は,有名人や芸能人だけでなく,一般人や個人経営のお店などがターゲットにされることも少なくありません。
インターネット・SNSにおける誹謗中傷の解決策
誹謗中傷などを抑制するためには,インターネットリテラシーの教育が有効であると考えられています。
とくに,誹謗中傷に関するリテラシーを整備・強化して,インターネットユーザーのリテラシーを向上させることが最も効果的であると思います。
インターネットリテラシーの向上によって,コメントを書き込む側が十分に注意する事,発言に責任をもつこと,
書き込みを目にする側も一部の情報を鵜呑みにせず,正確な情報を選択するということなどを促進することができます。
ただ,それでも誹謗中傷が完全になくなることはないと思います。
厳罰化が進んでも,犯罪事件が0になることはないのと同じように誹謗中傷も完全にはなくなりません。
必ず違反するユーザーが現れます。
そういった方々に対しては,法的措置が有効であると考えられます。
匿名で誹謗中傷行為をした加害者が訴えられるケースも増えていますし,
被害を受けた方は積極的に法的措置を講じるべきでしょう。
今後,誹謗中傷行為に対しては厳罰化されていくと考えられています。
※2022年6月13日,インターネット上の誹謗中傷対策として,「侮辱罪」を厳罰化する改正刑法が参院本会議で可決され,成立しました。同年7月7日より,侮辱罪の法定刑が引き上げられ,厳罰化されました。
まとめ

IT(Information Technology)は日々進化を遂げていますから,
コミュニケーションの技術やスタイルの変化に人間がついていけていないのが現状です。
今後どんなコミュニケーション・ツールが生まれるか分かりませんから,
対面でのコミュニケーションにおける礼儀作法と同じように,コミュニケーションの根底にあるモラルの早期教育が必要だと思います。
インターネットリテラシー等と同時に,人との繋がり方や距離感を具体的に教育して,加害者にも被害者にもさせないことが大切です。
そして,社会全体の目で監視や通報,誹謗中傷を抑制・対処するシステム作りが必要であり,
社会全体の意識を向上させることによって,誹謗中傷を減らすことができます。
誹謗中傷をしないこと,それは自分自身も誹謗中傷をされない権利でもあります。
悪意ある誹謗中傷が減少して,中傷によって傷つけられる方,また加害者になって取返しのつかない状況になってしまう方が少しでも減る事を願っております。
 セシル
セシルこの記事が気に入ったらぜひシェアしてくださいね🍀
\ おすすめの本・電子書籍はこちら!/
【引用文献・参考文献】
スーパー大辞林 (三省堂書店)
田中 辰雄・山口 真一 (2016) . ネット炎上の研究
——誰があおり,どう対処するのか—— 勁草書房
山口 真一 (2015) . 実証分析による炎上の実態と
炎上加担者属性の検証 情報通信学会誌, 33, 53-65.






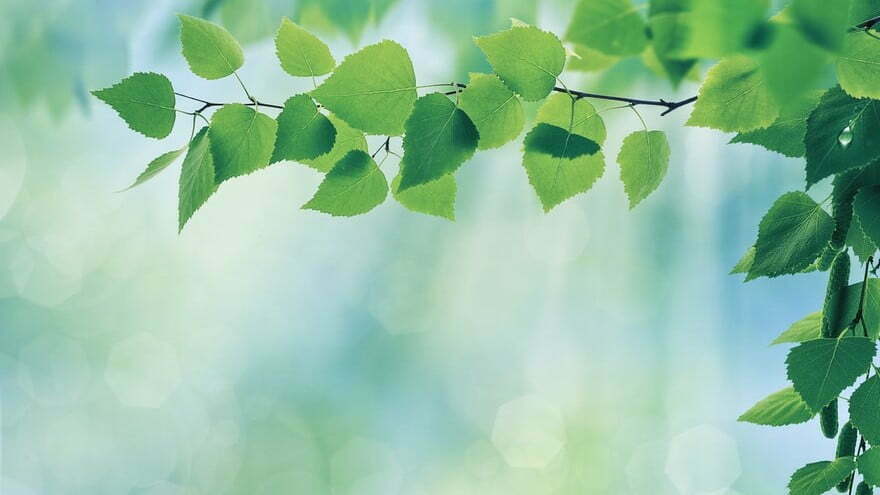











コメントを書いてみよう (^○^)