 セシル
セシルこんにちは,心理ブロガーのセシルです🍀
今回は「ひきこもりの子どもへの接し方と配慮の方法」について,主にひきこもりのお子さんのいる親御さんに向けて,元ひきこもりの私からアドバイスをさせていただきます。
『ひきこもり』とは??

『ひきこもり』とは,仕事や学校などの社会生活を送らず,家の中にひきこもってしまうことです。
ほとんど外出することがないか,自分の部屋からほとんど出てこないなどの場合があります。
私の場合,高校卒業と同時に18歳から20歳までひきこもり,20歳の時に大学に進学したことで,ひきこもりから脱することができました。
ひきこもっていた期間は,本当につらい時間でした。
私はほとんどの時間を自分の部屋で過ごし,10年くらい独房にいたような気持ちでした。
母子家庭で兄は下宿しており,小さな家で母と私で生活していました。
ひきこもり中は,母との喧嘩が絶えず,家庭も荒れていました。
母には迷惑をかけてしまったと思っております。
今回は,主にひきこもりのお子さんへの接し方や配慮に重点を置きますが,具体的な社会復帰の方法などについては下記の記事をご覧ください。
ひきこもりの子どもへの接し方と配慮の方法(体験談)
子どものことを理解して受け入れてあげること

まず,お子さんの現在の状態を受け入れて,お子さんを認めてあげてください。
これから先,希望する大学に行けなくても,大学に進学できなくても,失敗しても,たとえ犯罪者になってしまっても,親だけは子どものことを認めてあげてください。
もし,お子さんがひきこもりの状態を恥じているとしたら,ほとんどの場合,親御さんがひきこもりや精神疾患などに偏見をもっている場合が多いです。
親の価値観は子どもに継承されるからです。
外の世界は,家の中よりもはるかに多くの刺激や人との出会いに溢れています。
それでもひきこもりを選択せざるを得ないということは「きっとそれなりの事情があるのだろう」と,お子さんを1人の人間として尊重してあげてください。
子どもに言っていいこと
身嗜みを清潔にさせる

身嗜みや清潔感は非常に重要です。
歯磨きや入浴等については,ある程度口うるさく言ってもよいと思います。
後の社会復帰にとって非常に重要なことだからです。
一度だらしない癖をつけてしまうと,改善するのに苦労しますし,相当な時間がかかります。
それに清潔感がないと人が離れていってしまいます。
家から出なくなると,自然とお風呂に入る回数が減ったり,生活習慣が乱れていきます。
生活習慣に関しては,社会復帰する時に自然に整うものなので,昼夜逆転していてもそれほど気にしなくていいと思います(私の経験上,無理に変えようとしても,苦しむだけで続きませんでした)。
ただし,身嗜みだけは清潔にさせてください。
歯磨き,洗顔,入浴,着替え,男の子なら髭剃りなどです。
本人の力で部屋の掃除もできると尚良いですね。
※お子さんが「うつ病」や「うつ状態」の可能性がある場合は,ベッドから起き上がれない状態であることも少なくないため,その場合は特別な配慮が必要です。心療内科・精神科の受診をお勧めいたします。
勉強や仕事について

勉強や仕事に関することでプレッシャーをかけすぎるのは良くありません。
勉強についていけないことや仕事上での問題が原因でひきこもってしまった場合もあるからです。
ただ,いつかは社会復帰することを念頭に置くなら,時期を見て少しずつ話していく必要があるでしょう。
勉強や仕事のいずれかは,どんなに辛くても避けては通れない道だからです。
その際,話し方にコツが必要です。
決してお子さんのプライドを傷つけないであげてくださいね。
「勉強しなくてどうするの?」
「大学ぐらい行かないと」
「大学に行けなかったらどうするの?」
「就職できなかったらどうするの?」
など,お子さんを追い詰める言い方はやめてくださいね。
それよりも,勉強や仕事をすることで得られるメリットを楽しそうに教えてあげてください。
あくまで,責めるのではなく励ますのです。
\ 不登校のお子さんを支援するサービスはこちら!/


\ 通信制高校のパンフレット無料請求はこちら!/

\ 精神疾患や障碍のある方のための『就労移行支援』/
ひきこもりの理由を知る

ひきこもった理由や原因を知る必要があれば,本人に直接聞いてみるのでもよいですが,話してくれないケースは多いと思います。
その時は,親御さんがお子さんと同じ年ごろの時にどうしていたか,どんなことに悩んでいたかなどを毎日お子さんに話してみましょう。
お子さんも話を聞いているうちに,自分の話がしたくなることがあります。
その際,お子さんが話してくれたことは,守秘義務のある医師やカウンセラーの先生方以外の第三者には勝手に話さないように注意してくださいね。
お子さんにもプライバシーがありますから。
ただし,心の悩みなどは基本的に人に言えないものです。
むしろ知られたくないからこそ,大切に悩み続けるということもあります。
とくに,異性の親には,人間関係や恋愛関係などの問題について詮索されたくないものです。
子どもが話したがらないのなら,無理に理由を知る必要はありません。
「そういう時期かな」と割り切って,他のサポートにエネルギーを使いましょう。
他の家族を教育する

兄弟・姉妹など,他の家族がひきこもっているお子さんに対して無理解であったり,攻撃的である場合は,非常に足を引っ張ります。
1人だけ特別扱いしようというのではなく「人にはそういう時がある」,「あなたたちがなっても同じ」というふうに社会勉強として教育してあげてください。
偏見をもたず,懐の広い大人に成長することは,他の子どもたちにとってもプラスになります。
子どもに言ってはいけないこと
「ひきこもり」という言葉

子どもに言ってはいけないこと,それは「ひきこもり」という言葉です。
当サイトでは,便宜上「ひきこもり」という言葉を使用しておりますが,この言葉は基本的に言わない方が良いでしょう。
あなたが「ひきこもり」と言われたら,どんな気持ちになるか想像してみてください。
たとえ,あなたに他意はなくても「ひきこもり」という言葉には多くの偏見や差別などの意味合いも含まれています。
世の中には,蔑称のように使用する無理解な方もおられます。
他にも,いじめ被害を受けている子が「いじめられっ子」と表現されたり,
精神疾患を抱えている方が「病気」と言われてどんな気持ちになるかを考えれば,すべて同じことですね。
誰にでもプライドはあります。
イタズラに子どものプライドを傷つけないように注意してあげてくださいね。
親の苦しみ

お子さんに「あなたのせいで苦しんでいる」,「どうして分かってくれないの!!」などということを絶対に言ってはいけません。
少し厳しい言い方かもしれませんが,親が子どもに理解してほしいという状態になったら,もう子どもには尊敬されません。
子どもとの喧嘩も耐えなくなります。
子どもに親の自己愛を見せるのはやめましょう。
子どもが親を尊敬していないとすれば,それは子どもの問題ではなく,親の問題であることが多いです。
ひきこもりの子どもへの接し方と配慮の方法(体験談):まとめ
『ひきこもり』といっても,さまざまなパターンがあるため,非常に難しいテーマです。
本記事では,あくまで私の体験談をもとにお話しさせていただいております。
お子さんが心に傷を負っていたり,社会不安障害(SAD,対人恐怖症)などの病気になっている場合は,適切な治療や専門家のサポートも必要です。
しかし,ずっと必要以上に甘やかし続ける必要はありません。
これは甘いかどうかの精神論ではなく,元ひきこもりの私の経験上,
社会復帰には,ある程度の厳しさや現実と向き合う時間や訓練も必要だと実感しているからです。
というのも,医師やカウンセラーの先生方,親御さんに特別な配慮をしてもらっても,
社会復帰すれば,良い事だけではなく,傷つく戦いも待っているからです。
ひきこもり経験者の私だからこそ言える事ですが,社会復帰後に「ひきこもり」であったことをカミングアウトしたとしても,周りから特別にやさしくし続けてもらえるなんてことはありません。
厳しい競争もあれば,苦手なことを避けられない機会もありますし,いじわるな人,悪い人もいます。
人生において一度も傷つくことなく,ストレスもなく生きていくことはできません。
社会復帰してから,エネルギー全開で頑張ることも,ゆっくり着実に一つ一つ克服・達成していくことも,もちろん良い事です。
ただし,挫折しないためには,頑張ること以上に,つらいことに耐えたり,
あるいは「人生とはそういうものだ」という悟りを得ることのほうが大切です。
まず優しさや配慮を受けて回復して,他人や人生は思い通りにならないという現実を受け入れることが,社会復帰で挫折しないために必要な教訓です。
最後に,ひきこもりは難しい問題であり,物事にはそれなりの理由があります。
簡単に解決できる問題ではないということをご理解いただけましたら幸いです。
そして,親御さんにもいつも明るく元気でいてほしいですから,月に1回は映画に行くなど,適度に自分の時間も大切にして過ごしてくださいね。
お子さんのことだけに囚われてしまって,共倒れしたら元も子もないですからね。
 セシル
セシル いかがでしたでしょうか。
あなたの抱えていることが少しでも良い方へ向かうことを願っております。
この記事が気に入ったらぜひシェアしてくださいね🍀



\ おすすめの『カウンセリング』はこちら /





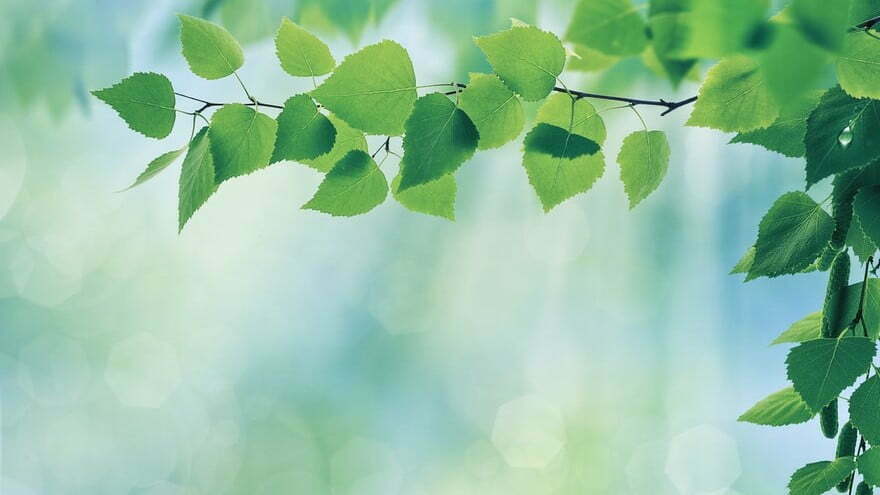








コメントを書いてみよう (^○^)