 セシル
セシルこんにちは,心理ブロガーのセシルです🍀
今回は,「男性は女性よりも生きづらい!? ~ 男性のほうが多く自殺している社会の真実~」についてお話しさせていただきます。
本記事では,男性の生きづらさや男性の自殺率の高さに焦点を当てておりますが,決して女性を差別する意図はございません。
あくまで一個人の考察としてご覧いただけましたら幸いです。
自殺率について
日本は,自殺死亡率が主要先進国の中で最も高い国です(厚生労働省,2022)。
そして,男性の自殺は例年減少傾向が続き,女性の自殺は増加傾向が見られるものの,男性の自殺者数は女性の約2倍です(警察庁,2022)。
皆さんは女性よりも男性のほうが多く自殺しているという事実をご存知でしたでしょうか?
テレビの報道等において,男性の自殺率の高さについてはあまり取り上げられていないように感じられます。
本記事では,なぜ男性がこんなにも自殺しているのか?? なぜ男性はこんなにも生きづらいのか?? ということについて考察させていただきます。
男性は女性よりも生きづらい!? ~ 男性のほうが多く自殺している社会の真実~
現代はストレス社会です。
老若男女問わず,誰もが生きづらさを抱えている時代です。
では,なぜ男性のほうが多く自殺しているのでしょうか??
その背景には,現代にも根強く残る『男性規範』の影響があると考えられます。
男性規範とは,「男は男らしく」,「男は強くなければならない」,「男なら弱音を吐くな」などといった考え方や風潮のことです。
男性本人の考え方に加えて,周囲の人からも「男のくせに」などとプレッシャーをかけられる風潮があります。
男性規範が男性を追い詰めているといっても過言ではありません。
それでは,具体的に男性が生きづらい,男性の自殺率が高い理由について考えていきたいと思います。
誰かを頼れない
テレビ等の自殺に関する報道では,「一人で悩まずに誰かに相談して」とよく言われますが,男性は比較的,人を頼るのが苦手です。
男性規範が影響して,助けを求めにくいのです。
私が公認心理師の先生方にお話を聞かせていただいた際も,男性はカウンセリングを受けることに抵抗のある方が少なくないとのことでした。
人生において困難や生きづらさを抱えていても,男性が人を頼ることができないということが男性を苦しめていると考えられます。
弱音を吐けない
男性は比較的,弱音を吐けない傾向があります。
人前で泣くことを恥として教育されて育った背景もあります。
女性が涙目で落ち込んでいると周りの皆が心配してくれることが比較的多いのですが,男性の場合は笑われて,軽蔑されることすらあります。
これは大人になるほど顕著になりますし,私も男性ゆえに弱音を吐けない職場や研究室にいたことがあります。
男性が”弱さ”を見せることは,社会からも本人からも比較的容認されづらい傾向があります。
交際のハードルが高い
男性は比較的,交際のハードルが高いです。
大人の男性は,結婚を見据えて,収入や将来性が問われる傾向があるからです。
男性側に自信がなければ,なかなか意中の相手にアプローチすることができません。
現代では,非正規雇用や無職・ニートなどが社会問題となっており,多くの男性が自信を喪失しています。
社会における男女不平等は,男性は女性よりも優位に立たなければならないという風潮を生じさせるために,女性だけではなく男性自身も苦しめていると考えられます。
結婚のハードルが高い
交際のハードルが高いのと同様に,男性は結婚のハードルが非常に高いです。
交際相手がいても,収入や将来性に乏しい男性の場合,なかなか結婚を申し込むことができない状況があります。
一人前の男性として認められる自信がなければ,相手側のご両親に挨拶に行くことすら躊躇われます。
逆に,女性の収入や地位を理由に結婚が難しいという話はほとんど聞いたことがありません。
このことも晩婚化の一因になっていると考えられます。
失業のダメージが大きい
警察庁が発表した「令和3年中における自殺の状況」では,「経済・生活問題」を原因・動機とした自殺者数が男性が2,922人,女性が454人で,男性は女性の約6.4倍多く自殺しています(警察庁,2022)。
失業や若者の就職活動の失敗などが,男性に比較的大きなダメージを与えていることは明らかです。
現在は男女共働きが増えていますが,男性が正社員として働いて家庭を支えるべきだという伝統が根強く残っていることが背景にあると考えられます。
社会において,女性が家計を支えて,男性が専業主婦をすることへの偏見や抵抗はまだまだあります。
また,「勤務問題」を原因・動機とした自殺者数が男性が1,628人,女性が307人で,男性が女性の約5.3倍多く自殺しています(警察庁,2022)。
勤務問題においては,一概には言えませんが,男性のほうが社会での風当たりがきつい傾向があるため,パワハラ被害などの影響が考えられます。
地元に帰れない(余談)
こちらは余談ですが,夢を見て上京した若い男性が成功できていないことを理由に地元に帰りづらいということもよくあるお話です。
こうしたことも男性の孤独感を高めている可能性があります。
同窓会や結婚式に出席できない(余談)
こちらも余談ですが,男性はある程度の社会的成功をおさめていないと,同窓会や結婚式に出席しづらいというのもよく聞くお話です。
たとえば,同窓会では「私はこんな仕事をしています」,「子どもが大きくなって~」などと自信をもって自己紹介ができる方が出席しやすいのに対して,そうではない方は敬遠されている傾向があるのではないでしょうか。
このように,社会的に認められないことが男性の孤立を促進させる可能性があります。
孤独である
ひきこもりの方の数は,圧倒的に男性のほうが多いです(内閣府,2019)。
ひきこもりが長期化すると,社会から孤立していきます。
孤独に対する耐性に男女差がなかったとしても,そもそも男性の方が孤立しやすいという傾向があります。
助けてもらえない
男性は比較的,誰かを頼ることができず,弱音も吐けないということを述べてきましたが,実際に男性は女性よりもはるかに助けてもらえた経験が少ないと思われます。
当然かもしれませんが,たとえば災害時では,女性や子ども,高齢者などから優先して救助される傾向があります。
健常な男性が後回しにされる傾向があり,女性や子どもよりも我先にという男性は軽蔑されてしまうでしょう。
精神的な支援においても同様です。
男性が誰かに助けを求めたり,弱音を吐いたりすることで,実際に助けてもらえることが予測できれば,男性も救助を要請しやすくなると考えられます。
助けを求めても良い結果にはならないという現状も男性が助けを求めにくい理由であると思われます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「男性は女性よりも生きづらい!? ~ 男性のほうが多く自殺している社会の真実~」についてお話しさせていただきました。
あくまで私個人の考察であり,他にも男性のほうが自殺者数が多い理由は考えられると思います。
また,男性ほうが自殺者数が多いという現状はあるものの,女性の自殺者数の増加も深刻な社会問題になっています。
繰り返しますが,現代はストレス社会であり,誰もが生きづらさを抱えています。
本記事が「誰もが生きやすい社会になるためにはどうすればよいか」ということを考えるきっかけになりましたら幸いです。
 セシル
セシル 私も「消えたい」,「死にたい」と思い続けている時期がありました。
それでも生き抜いてきたことで,強くなれたと思っております。
つらい思いをされている方にこそ,これからたくさん幸せになってほしいと願っております。
またいつでも当サイトに遊びに来てくださいね🍀
この記事にご共感いただけましたら,シェアをよろしくお願いいたします🍀


\ 今すぐ仕事を辞めたいあなたの味方です!/

\ おすすめの『カウンセリング』はこちら /

\ 精神疾患や障碍のある方のための『就労移行支援』/
【引用文献】
警察庁 (2022) . 令和3年中における自殺の状況
厚生労働省自殺対策推進室 警察庁生活安全
局生活安全企画課 Retrieved from https://
www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu
/R04/R3jisatsunojoukyou.pdf
(2023年3月10日)
厚生労働省 (2022) . まもろうよ こころ
自殺対策の今 自殺対策の概要
厚生労働省ウェブサイト Retrieved from
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyoko
koro/taisaku/sesakugaiyou/
(2023年3月10日)
内閣府 (2019) . 子供・若者白書 内閣府
特集2 長期化するひきこもりの実態
内閣府ウェブサイト Retrieved from
https://www8.cao.go.jp/youth/whit
epaper/r01gaiyou/pdf/b1_00_02.pdf
(2023年3月10日)




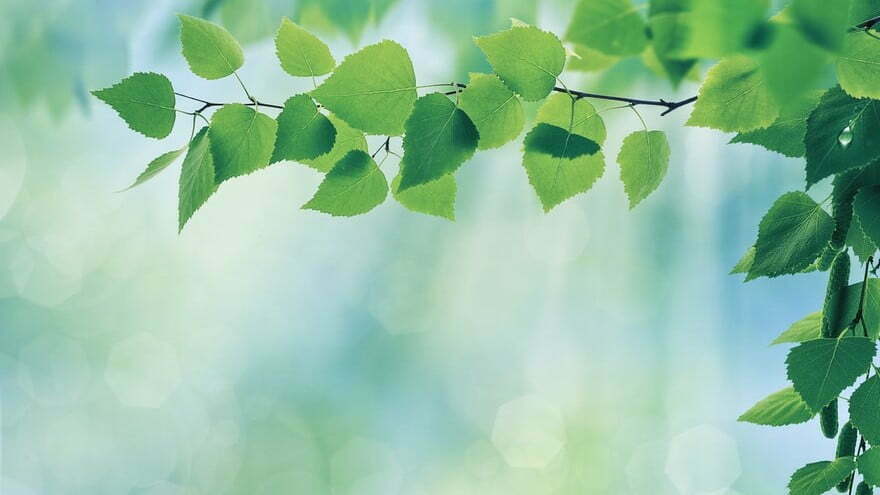








コメントを書いてみよう (^○^)